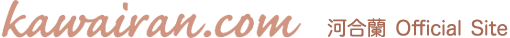大垣文化事業団の朗読会と展示解説が終わったあと、事業団の鈴木さんに無理を言って父の生家に連れて行ってもらいました。実は、私の父は自分の生家に、私を連れて行くことはついにありませんでした。
しかし、それでは子どもが自分がどこから来たのかわからなくて困るだろう、と、父の死後に、父の弟(私の叔父のあたる人で私が所在をわかっていた父方の唯一の肉親)が、簡単に案内してくれたことがあります。しかし、二十歳そこそこだった私は住所を記録しておくこともなく「ふーん」と思う程度で帰ってきてしまい、その後に叔父も亡くなるとそこがどこであったのかもわからなくなっていました。
しかし父は、土手のある川がすぐそばを流れ、田んぼが続いていた自分のふるさとや、自宅のことをたくさんの随筆に書き残しました。県人会の会誌や、自分が仕事で編集していた専門誌の埋め草に載せていたのです。父が書き直したものはおもに故郷のことと新美南吉と過ごした東京外語時代の思い出です。
父は田んぼの真ん中の中学から東京外語大学の進学を志し、どういうわけか入試に成功し上京。当時外語があった神田界隈で南吉に声をかけられ、毎日行動を共にするようになりました。そして新美さんがかかった結核をもらってしまいます。
卒業の直後に結核という当時の不治の病を宣告された父にとって、故郷は闘病の地でもありました。闘病中に新美さんが愛知県の半田からお見舞いに来てくれたようです。その時は新美さんの方がよかったのでしょう。しかし新美さんの病状はその後悪化して、父に、ひと思いに死ねる薬を送れと書いてきて、それを父が断るとすぐに「君と絶交する」という手紙が来たそうです。それが父と新美さんの交友の終わりでした。その数日後に、父は新美さんの兄弟から黒枠の葉書をもらいました。
もう君の字でないことが悲しかった
父はそう書いています。そして、その父は生きのびて東京に帰ってきて母と結婚し、44歳の時に、当時としては孫のように年が離れた私が生まれることになりました。父が出たのは、腹違いのきょうだいの間がうまくいかなくなったためのようです。
私は父が死んだときの父の遺稿集を編みましたが、ラストは子ども時代の父が堤の道をお母さんを追ってひとりで歩いて町に行き、夜が暮れてからお母さんと叔母車を引いて帰ってくるという短編にしました。
もう、ようさりになってしまったん
父のお母さんはそう言って、父の手を引いてゴトゴトとおば車を押していきました。父のおかあさんは、大垣の中心にある、皆が湧き水を汲みに来る八幡さまのそばに実家があり、そこに用事に行っていました。
その堤の道に上がったとき、私にこみ上げてきたものは、ここだ、こここそが父の原風景だという揺るぎのない確信と、やっとここに帰ってくることができたという喜びでした。懐かしくて、懐かしくて涙が止まりませんでした。それは不思議なことに、限りなく「記憶」に近いものでした。
2015/10/17