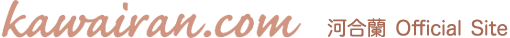妊娠中に赤ちゃんの病気を調べる出生前検査について、国の方針が変わりました。6月9日、出生前検査については「情報提供を行なうべきである」と明記された通知が、厚労省の母子保健課長、障害福祉課長の連名で全国の自治体へ向けて送られました。
驚異的な精度の血液検査「新型出生前診断(非侵襲性出生前遺伝学的検査(NIPT : Non Invasive Prenatal Testing)」が2013年4月に国内で開始されてから、ちょうど8年目の変更です。

これまで、国としての方針は1999年に出された見解によって示されていて、それは、出生前診断は妊婦に「知らせる必要はない」というものでした。しかし、もはや出生全体の3分の1を占める高齢妊娠女性たちにとっては、染色体異常の子どもが生まれるかもしれないという心配は最大の不安で、ちゃんとした情報や、陽性になった時の支援をしてくれる体制作りを求めています。反対運動があるから正規のサービスはしません、皆さんがめいめいにどうぞ、ということでは、妊婦はネットの海をひとりでさまようしかありません。
今、美容外科医などによるNIPTの無認可クリニックがネットでたくさんの妊婦さんを集め、社会問題となっていますが、その背景には、そもそも日本の母子保健の体制に、出生前検査がちゃんとした居場所を与えられていなかったという問題があります。
「知らせる必要はない」という考えは、当時の専門委員会がそうした見解をまとめたのですが、私は自分がちょうど高齢妊娠で第三子を出産した頃でした。当時、その見解の内容に、不安な妊婦の立場への配慮が感じられなかった私は、医療職と新聞社と障害者団体が妊婦のことを決めてしまったという想いが湧き、当時のこの国の、妊婦を蚊帳の外に置いたマタニティ政策にジャーナリストとしてとても失望しました。
そんな思いが原動力になって、日本にNIPTが上陸した時、私は『出生前診断~出産ジャーナリストが見つめた現状と未来』のオファーを思い切って受けました。当時は今より出生前検査に対する非難が強かったですけれど、何か月も考えた末にこの難しいテーマに取りくみました。
今回、私は、厚労省の新しい専門委員会にメンバーとして指名していただき、女性の立場を十分に語らせていただきました。私は過去の専門委員会の議事録を穴が開くほど読んで『出生前診断~出産ジャーナリストが見つめた現状と未来』の第三章はそれに終始していますから、後世の方がどれだけ批判なさるかわからないとは思いましたが、そんなこと考えていては自分が今すべきことできません。
私は母子保健の仕組みの中に出生前検査や胎児をちゃんと入れていただきたいし、産科医、臨床遺伝専門医、遺伝カウンセラーにとどまらず、助産師さん、保健師さん、心理職の方、福祉関係の方、ピアカウンセラーさんも入った輪の中で検査前後のフォローもおこなわれてほしいとお話しさせていただきました。この部分は、しっかり報告書の中に入れていただいてとてもうれしかったし、これが地域でも、そして医療施設の中でも本当に実現するところまでしっかり見届けたいという気持ちが今強くなっています。
ここには、出生前検査を、よりよい環境で出産するための準備としてとらえるという発想がベースに必要となりますが、それは2年間ほどの間にFRaUの連載「出生前診断と母たち」でお会いしてきたたくさんのお母さんたちにお話を聞いて、時にはご出産に立ち会ったりしてきて、その時間の中で私も変化してきました。
もともとNICU(新生児集中治療室)の取材の中で、たくさんの赤ちゃんが、胎児診断のメリットを受けたり、胎児診断がなかったために大変なことになったりしているのは見ていました。振り返ると出生前検査について私が今考えていることは、一件バラバラに見えるさまざまな取材――助産、周産期センター、不妊治療、高齢出産などのすべてが環となったような、そんな感覚があります。
■新しい方針については、通知書も含めてこちら(出生前検査及び流産死産のグリーフケアに関する自治体説明会の案内ページ)にまとめられています。