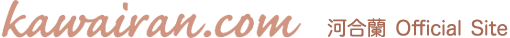8月25日に同居していた実母を亡くしました。早いもので、もう半月が過ぎました。
83歳だった母は、今年のある春の日、庭のさくらに見とれて枝を手折りたいと思ったのです。そして庭にあった椅子に乗って手を伸ばしてしまったので転倒して骨折しました。転ぶのがこわくて人に頼ったばかりいた母がなぜそんなことをしたのか、それはさくらを通じて何かが語りかけたのかも知れません。さあ、あなたに時期が来たのです、と。
家でじっとしていられない性分の母は電動二輪車に乗ってよく出歩いていたのですが、それ以降閉じこもる毎日になり、認知症が一挙に進行しました。4月に見えた介護認定をする方が「私は何百人もこういう方を見てきましたが、あなたにはこれからびっくりすることがたくさん起きますよ」と的確に予言していきました。その予言は見事に当たりました。
母はそれまでも強い性格で家族を振り回しましたがその傾向はますます強くなりました。どんどん子どもへと退行し、さらに脳は壊れて片時も家にひとりでおいておくことができない状態になりました。しかし、インシュリンを打っていて、肝臓がんもあった母を受け入れてくれる施設はなかなか見つかりませんでした。
そんな母に再び手招きがありました。梅雨もおしまいになるある日、自分は誘拐犯にとらわれているという妄想を持った母は、ドアを開けて家を出て行ったのです。
私と母の別れは、拘束と施錠とそしてトランキライザーの日々でした。別にずっと拘束されていたわけではないのですが、やはり強烈な印象になって残ります。これらのすべては、私が家庭裁判所で母の人権を奪ったことで法の下のこととなりました。
うなぎを食べたことを日記に書きましたか、あれはトランキライザーが見せてくれた私たちの最良の時間でした。薬の力を借りてしかあり得ない幻だったかもしれません。でも、生きていることはそれ自体が幻であるような気もします。お酒の力を借りて恋をする人もいる。それと同じだと思います。
そのあと、少しずつ母は身体的に弱っていき、トランキライザーの使用が中止になって症状が戻ってきてしまいました。ただ、エネルギーもなくなってきたので極端なことはもうせず、また脳の変化のために自分の症状を深刻にとらえて悲しむこともなく、のんきにベッドで気宇壮大なことを言っていました。やせ衰えるということもなかったので、私はまだ先だと思っていたのですが、ある晩、真夜中に病院から電話が鳴る事態となりました。
夜明けを待って、母が何年も前から決めていた教会に電話をしました。最近何度かかけていたのにいつも不在で困っていたのに、その朝、牧師さんがすぐに出てきたときは本当にびっくりでした。しかも、翌日からは幼稚園のキャンプで不在だったと言います。あの朝だったということも、何かの手招きだったのかもしれません。
教会は明治に創立、関東大震災で建て直された本郷中央教会。三方をガラス窓に囲まれた横長の礼拝堂はゆったりと人を包み込むようで、足を踏み入れたとたん私は魅了されてしまいました。母はこの幼稚園を出ていて、クリスマス会でマリア様を演じた写真を大事に持っていました。
葬儀の式は、20年くらい前の定年退職まで結核の研究者だった母の一生のおつきあいの方々とお会いしてタイムマシンさながら。懐かしさで一杯になりました。
牧師さんに母の経歴を渡すと一生懸命に読みこんでくださり、本当にいい式をとりおこなってくださいました。最後に母の身体を空に返すとき、見送る人たちの力強い賛美歌でまもりました。
そして母はあんなに強かったもろもろの執着からついに解放されて、自由に透明になりました。
あんなに私に抵抗していた母だけれど、真っ白な十字架のついた黒いサテンに包まれた母の骨を抱くと、私の腕の中にすっぽりと収まり、暖かでした。
その夜、一番下の子がこんなことを言いました。
「死ぬのがこわくなくなった。今日、こわくなくなったの」
いいことがひとつでもあればいい。うなぎの日もあったし、いいお葬式もできた。
母は私を産んだときも、育てたときもみんなあまりうまくいかなくて、だから私は今こんな仕事をしているのかと思います。でも私は今は、世の、ごく普通の傷だらけの親子に拍手を送りたい気もするのです。どんな親子でも、宝物ひとつはあるはずだから。
専門家は理想の親子を語ることは要らず、そのひとつを手伝うことができれば、それでいいのではないでしょうか。 2008/09/11